【消えた偉人・物語】 大和生存者 吉田満
「死者」不在の戦後教育
沖縄特攻で沈没した戦艦大和の生存者である吉田満は、「戦没学徒の遺産」(昭和44年)という文章を残している。特にこの夏は、次の言葉を何度も何度も思い出した。
「私はいまでも、ときおり奇妙な幻覚にとらわれることがある。それは、彼ら戦没学徒の亡霊が、戦後二十四年をへた日本の上を、いま繁栄の頂点にある日本の街を、さ迷い歩いている光景である。(中略)彼らが身を以て守ろうとした“いじらしい子供たち”は今どのように成人したのか。日本の“清らかさ、高さ、尊さ、美しさ”は、戦後の世界にどんな花を咲かせたのか。それを見とどけなければ、彼らは死んでも死にきれないはずである」
さらに「彼らの亡霊は、いま何を見るか、商店の店先で、学校で、家庭で、国会で、また新聞のトップ記事に、何を見出すだろうか。戦争で死んだ時の自分と同じ年頃の青年男女を見た時、亡霊は何を考えるだろうか」と問う。
そして「もしこの豊かな自由と平和と、それを支える繁栄と成長力とが、単に自己の利益中心に、快適な生活を守るためだけに費やされるならば、戦後の時代は、ひとかけらの人間らしさも与えられなかった戦時下の時代よりも、より不毛であり、不幸であると訴えるであろう」と続けた。
戦後教育は「死者」を忌避し、「死者からの視線」を欠落させてきた。「死者」との絆は、「戦前=悪」「戦後=善」という歪(ゆが)んだ歴史教育によって意図的に切断されるか、「死者」の「思い」を正確に「教えない」ことで「生者」とのつながりを断絶させてきた。
戦後教育のいう「人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念」とは、いま生きている「生命」にのみ焦点が合わされ、自らの生命の礎となった「死者」の存在とその「思い」に目を向けることはなかった。しかし、「死者」の「思い」を無視した教育は、たやすく無機質な「生命尊重主義」に回収されてしまい、ここから真の「畏敬の念」が生まれることはない。
「死者」の「思い」を無視することは、「死者」に対する
倫理の崩壊であり、「死者からの視線」を実感しながら
生きることなしに、日本人の道徳の再生はない。
(武蔵野大学教授 貝塚茂樹)

http://storymachine.blog65.fc2.com/blog-date-20120904.html
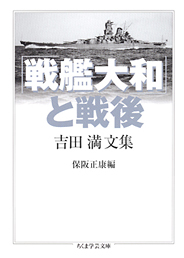
1945年4月、大日本帝国の象徴、戦艦「大和」は沖縄に向かう特攻作戦を行なった。この戦いで九死に一生を得た著者は、その極限の体験を名著『戦艦大和ノ最期』として発表。死地に赴いた兵士たちは、葛藤のなか、死ぬことの意義を見出そうと煩悶する。「大和」出撃から戦闘、沈没までを、明晰な意識のもと冷静な筆致で描くことにより、戦争とはいかなるものかが如実に表わされ、その背後に戦争の虚しさが漂う。後に著者は、戦いに散華した者の死の意味を問い続け、戦後日本の在り方に対して意義を唱える。戦争と平和、日本という国、日本人の生き方を問う著者渾身のエッセイを集成。
