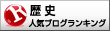大虐殺があったのなら感謝されない。

昭和12年(1937年)の支那事変南京戦では海軍も参加していました。あまり知られていないかもしれません。海軍第11戦隊が揚子江を上り、12月13日には南京に到着しています。陸地から攻撃してくる支那軍に砲撃を加え、揚子江上を敗走する支那軍の舟艇を銃撃しています。
砲艦勢多艦長 寺崎隆司少佐
「13日の午後3時15分です。中興碼頭には日本陸軍が来ていまして日の丸を振っていました。南京に着いたら陸軍と連絡せよと司令官から命令されていましたので、中興碼頭に向かうと保津に信号しましたら先頭の保津がすぐに中興碼頭に向かったので、勢多が先頭になり、さらに先の下関桟橋に向かいました。
下関桟橋に近づきますと多くの兵が手を振っているので、双眼鏡で見ますと中国兵なのです。中国兵は日本の軍艦がこんなに早く来るとは思わず、中国の軍艦だと思って手を振ったのだと思います。そこでまた二十五ミリ機銃で掃射して近づきました」(ここまでにジャンクや筏の支那兵に遭遇している)
「13日の午後3時15分です。中興碼頭には日本陸軍が来ていまして日の丸を振っていました。南京に着いたら陸軍と連絡せよと司令官から命令されていましたので、中興碼頭に向かうと保津に信号しましたら先頭の保津がすぐに中興碼頭に向かったので、勢多が先頭になり、さらに先の下関桟橋に向かいました。
下関桟橋に近づきますと多くの兵が手を振っているので、双眼鏡で見ますと中国兵なのです。中国兵は日本の軍艦がこんなに早く来るとは思わず、中国の軍艦だと思って手を振ったのだと思います。そこでまた二十五ミリ機銃で掃射して近づきました」(ここまでにジャンクや筏の支那兵に遭遇している)
寺崎隆司少佐は翌年の7月まで南京にいましたが、もちろん南京虐殺など見ておりません。
砲艦勢多 次席大尉・関口鉱造 15日の南京偵察
「星条旗を掲げている建物(鼓楼病院)をのぞいたところ、年配の米国人(発音で米国人とすぐ判りました)が出てきたので城内の様子を訊ねました。この人がフィッチ氏であったのでしょう・・・彼の話を要約すると『城内(難民区?)は完全に非武装化され難民が溢れている。しかし、便衣に姿をかえた支那兵が潜入していることは事実である。難民の処理、治安の維持については米・英など第三国が斡旋して日本軍当局と交渉中である』・・・」
「城内(難民区)は女子供でゴッタ返していたが、若い男の姿はあまり見かけませんでした。時折り、窓越しに険悪な眼で注視している男を見かけましたが、便衣兵らしく思われました」
「『虐殺』などという事件は、艦長以下全乗組員とも目撃しておりません」
「星条旗を掲げている建物(鼓楼病院)をのぞいたところ、年配の米国人(発音で米国人とすぐ判りました)が出てきたので城内の様子を訊ねました。この人がフィッチ氏であったのでしょう・・・彼の話を要約すると『城内(難民区?)は完全に非武装化され難民が溢れている。しかし、便衣に姿をかえた支那兵が潜入していることは事実である。難民の処理、治安の維持については米・英など第三国が斡旋して日本軍当局と交渉中である』・・・」
「城内(難民区)は女子供でゴッタ返していたが、若い男の姿はあまり見かけませんでした。時折り、窓越しに険悪な眼で注視している男を見かけましたが、便衣兵らしく思われました」
「『虐殺』などという事件は、艦長以下全乗組員とも目撃しておりません」
南京陥落後、海軍は南京下関から1.8キロ離れた紅卍字会の保国寺難民区(難民と市民二万余り)に対して食料や被服を給与しています。そして敗残兵の掠奪から市民を守っていました。これに尽力したのが土井中佐で、救援物資が到着したとき、市民と難民は「南京下関平和街」の横断幕をはり爆竹をあげ、日の丸を掲げ、歓呼して迎えています。土井中佐に紅卍字会から感謝状が送られました。
紅卍字会 陳漢森の礼状
「・・・閣下の軍艦は江浜府に停泊する際、閣下は民衆が餓えている状況を察せられ、小麦粉と食用油を賜り、大勢の民衆の命をお助けになりました。また道路の整備と橋架けを命ぜられ、且つ自らご指導に当たられました。・・・」
「・・・閣下の軍艦は江浜府に停泊する際、閣下は民衆が餓えている状況を察せられ、小麦粉と食用油を賜り、大勢の民衆の命をお助けになりました。また道路の整備と橋架けを命ぜられ、且つ自らご指導に当たられました。・・・」
土井申二中佐
「私は第三艦隊艦隊司令部にいき、人道上、宝塔橋街をそのままにすることができない、といいました。すると長谷川清司令長官は宝塔橋街でやったことを非常に喜び、医療品や食料をくださいました。
(中略)
平和街が落ち着いた頃、比良(砲艦)は蕪湖の警備を命ぜられましたので中興碼頭を離れました。陳漢森(紅卍字会の代表者)はその後もわざわざ礼状をくれまして、終戦まで手紙のやりとりをしました。よっぽど感謝したものと思います」
「私は第三艦隊艦隊司令部にいき、人道上、宝塔橋街をそのままにすることができない、といいました。すると長谷川清司令長官は宝塔橋街でやったことを非常に喜び、医療品や食料をくださいました。
(中略)
平和街が落ち着いた頃、比良(砲艦)は蕪湖の警備を命ぜられましたので中興碼頭を離れました。陳漢森(紅卍字会の代表者)はその後もわざわざ礼状をくれまして、終戦まで手紙のやりとりをしました。よっぽど感謝したものと思います」
南京で30万人を虐殺するような日本軍に救援物資をくれただけで感謝してずっと手紙のやりとりをするはずがありません。日本軍は武士道の精神で行動していました。もちろん陸軍も同じで、脇坂部隊(歩兵36連隊)は13日夜、敵の戦死体をねんごろに埋葬し、一晩中読経をあげて弔いました。18日には陸海軍合同で慰霊祭を行っています。
参考文献
小学館文庫「『南京事件』日本人48人の証言」阿羅健一(著)
小学館文庫「『南京事件』の総括」田中正明(著)
日新報道「南京の実相」日本の前途と歴史教育を考える議員の会(監修)
偕行社編「証言による南京戦史」
小学館文庫「『南京事件』日本人48人の証言」阿羅健一(著)
小学館文庫「『南京事件』の総括」田中正明(著)
日新報道「南京の実相」日本の前途と歴史教育を考える議員の会(監修)
偕行社編「証言による南京戦史」
添付写真
中山門内故宮飛行場戦没勇士慰霊祭における海軍陸戦隊の敬礼(1937年12月18日)(PD)
中山門内故宮飛行場戦没勇士慰霊祭における海軍陸戦隊の敬礼(1937年12月18日)(PD)
 南京虐殺という大嘘
南京虐殺という大嘘