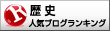南京陥落、市民は安全区に避難していた。

昭和12年(1937年)8月、第二次上海事変が勃発します。そして戦闘は12月には南京へ移行しました。そして南京大虐殺が発生したと言われています。本当にそうでしょうか。まずはリアルさを見るため、戦後焚書された書物で南京陥落時の様子を見てみます。
「画法躍進之日本」『南京陥落祝賀号』(GHQ焚書図書開封より)
「夜が明けるとすぐ城門への突入がはじまった。前方には城壁を取り巻いて幅30メートルほどのクリークがあった。クリークの土手は三間ほどの道路になっていて、そこに塹壕があった。城門はすでにピッタリ閉ざされて、泥や砂がいっぱい積んである。クリークの土手の敵は、場内に逃げ込む道はなかった。堪えかねてバタバタバタと城門へ走って行くが、片っ端から友軍の重機になぎ倒されて、山のように重なって倒れていく」
「夜が明けるとすぐ城門への突入がはじまった。前方には城壁を取り巻いて幅30メートルほどのクリークがあった。クリークの土手は三間ほどの道路になっていて、そこに塹壕があった。城門はすでにピッタリ閉ざされて、泥や砂がいっぱい積んである。クリークの土手の敵は、場内に逃げ込む道はなかった。堪えかねてバタバタバタと城門へ走って行くが、片っ端から友軍の重機になぎ倒されて、山のように重なって倒れていく」
南京は城壁で取り囲まれた街で、城壁の周りに堀のように川(クリーク)が流れています。その土手に支那兵がおり、日本軍の攻撃によって支那兵が城門へ走って逃げ込もうとしているところを、日本軍の重機が追い撃ちをかけているわけです。場所は南の中華門あたりです。そして、日本軍はクリークに渡河橋を投げ込み、城壁を爆破します。
「やがて城門を埋めた小山のような泥の坂のところで日章旗がしきりと打ち振られた。戦車は轟音をたてて動き、私たちもまた一斉に進軍した。
『十二時十二分!』
と小林伍長が叫ぶ。ただ敵の死体と散乱する軍需品の海だった。これを踏み越え踏み越え進むうち
『オイ、女だ!』
と石原上等兵が叫んだ。なんという唐突な言葉だったろう。大南京城が陥落の間際、最高潮の戦場で
『オイ、女だ!』
と叫ぶ。その唐突さにもかかわらず、いや唐突さゆえにか、男性である私はザクッと胸を刺されたように思った。私は石原上等兵をみた。石原上等兵は今一歩踏み越そうとした敵の死体の山をつくづく眺めている。敵の死体に混じって立派に軍装した、紛れもない断髪の女の死体が一つうずまっていた。閉ざされた中華門にすがりついて慟哭するかのような姿で、女が --- 女の兵隊がおびただしい支那兵と一緒に死んでいた」
『十二時十二分!』
と小林伍長が叫ぶ。ただ敵の死体と散乱する軍需品の海だった。これを踏み越え踏み越え進むうち
『オイ、女だ!』
と石原上等兵が叫んだ。なんという唐突な言葉だったろう。大南京城が陥落の間際、最高潮の戦場で
『オイ、女だ!』
と叫ぶ。その唐突さにもかかわらず、いや唐突さゆえにか、男性である私はザクッと胸を刺されたように思った。私は石原上等兵をみた。石原上等兵は今一歩踏み越そうとした敵の死体の山をつくづく眺めている。敵の死体に混じって立派に軍装した、紛れもない断髪の女の死体が一つうずまっていた。閉ざされた中華門にすがりついて慟哭するかのような姿で、女が --- 女の兵隊がおびただしい支那兵と一緒に死んでいた」
城門が閉ざされており、城内に逃げれず、門にすがるようにして女性兵士が死んでいたのです。日本兵士は衝撃だったでしょう。当時の日本人の常識としては女性を戦場で戦わせるなど考えられなかったわけです。
さて、東京裁判で言われたように日本軍は大挙、南京城内に乱入して大虐殺を開始したのでしょうか。中華門から入城したのは第六師団の第13連隊と第47連隊のそれぞれ1大隊です(第23連隊も入城の記録あり)。このとき大坂毎日新聞の五島広作記者が一緒に入城しています。
五島記者へのインタビュー
- 南京陥落後の第六師団の行動はどうでした。
五島記者「12日12時にはじめて城壁を占領し、13日、一部城内に入りました。私もこの時、第13連隊から選抜した部隊と城内に入りました」
- 南京陥落後の第六師団の行動はどうでした。
五島記者「12日12時にはじめて城壁を占領し、13日、一部城内に入りました。私もこの時、第13連隊から選抜した部隊と城内に入りました」
- この時、残虐行為などは?
五島記者「13日、14日は城内掃蕩で、残虐行為などありません」
五島記者「13日、14日は城内掃蕩で、残虐行為などありません」
- 南京には外国の記者が残っていましたが・・・
五島記者「ええ。何人かと会って話をしています」
五島記者「ええ。何人かと会って話をしています」
- その時、日本軍の軍紀について話題になったことがありませんか。
五島記者「彼らとそういう話をした記憶はありません。パラマウントのニュース映画が南京を撮っていて、私もそのニュース映画に映っています。撮ったのはアーサー・メンケンです」
五島記者「彼らとそういう話をした記憶はありません。パラマウントのニュース映画が南京を撮っていて、私もそのニュース映画に映っています。撮ったのはアーサー・メンケンです」
第47連隊と報知新聞の二村次郎カメラマンが入城しています。
- 城内はどうでした?
二村カメラマン「中国人は誰もいませんでした」
- 城内はどうでした?
二村カメラマン「中国人は誰もいませんでした」
- 南京虐殺ということが言われていますが・・・
二村カメラマン「南京にいる間見たことがありません。戦後、よく人から聞かれて、当時のことを思い出しますが、どういう虐殺なのか私が聞きたいくらいです」
二村カメラマン「南京にいる間見たことがありません。戦後、よく人から聞かれて、当時のことを思い出しますが、どういう虐殺なのか私が聞きたいくらいです」
第47連隊の速射砲中隊長の安部康彦氏は城外にいましたが、城内に入った掃討部隊から次のように聞いています。
「掃蕩部隊から聞いた話では、便意の敗残兵は、ほとんど退去した跡であり、掃蕩といっても遺棄された軍需品の収集や跡片づけが主な仕事であったとのことです」
「掃蕩部隊から聞いた話では、便意の敗残兵は、ほとんど退去した跡であり、掃蕩といっても遺棄された軍需品の収集や跡片づけが主な仕事であったとのことです」
第23連隊 坂本氏
「残敵を掃蕩するため、連隊主力は城壁に沿い、私の第二大隊はその東方の市街地を北方に向かって前進した。ちょうど12時頃、道路の左側に飲食店が店を開いており、主人らしい一人の男がいたので、支那ソバか何かを注文し・・・一々家屋を点検した訳ではないが、前記の飲食店の男以外には市民も敵兵も見ず、また大した銃声も聞かなかった」
「残敵を掃蕩するため、連隊主力は城壁に沿い、私の第二大隊はその東方の市街地を北方に向かって前進した。ちょうど12時頃、道路の左側に飲食店が店を開いており、主人らしい一人の男がいたので、支那ソバか何かを注文し・・・一々家屋を点検した訳ではないが、前記の飲食店の男以外には市民も敵兵も見ず、また大した銃声も聞かなかった」
南京には人がいなかったのです。支那兵は逃げ、市民は国際委員会が管理する中立地帯にいたのです。この地帯は第九師団の第七連隊の受け持ち地区で他の部隊は入ることはできませんでした。第六師団の一部が13日夕方にちょっと立ち寄った程度です。しかし、第六師団の師団長・谷寿夫中将は戦後、南京法廷で有罪判決となりました。
南京法廷 判決主文
「谷寿夫は作戦期間中、兵と共同してほしいままに捕虜および非戦闘員を虐殺し、強姦、略奪、財産の破壊をおこなったことにより死刑に処す」
「谷寿夫は作戦期間中、兵と共同してほしいままに捕虜および非戦闘員を虐殺し、強姦、略奪、財産の破壊をおこなったことにより死刑に処す」
無人地帯で大虐殺などできようはずがありません。
参考文献
徳間書店「GHQ焚書図書開封」西尾幹二(著)
小学館文庫「『南京事件』日本人48人の証言」阿羅健一(著)
展転者「南京事件の核心」冨澤繁信(著)
偕行社「証言による南京戦史」
青木書店「南京事件資料集 中国関係資料編」南京調査研究会(編訳)
徳間書店「GHQ焚書図書開封」西尾幹二(著)
小学館文庫「『南京事件』日本人48人の証言」阿羅健一(著)
展転者「南京事件の核心」冨澤繁信(著)
偕行社「証言による南京戦史」
青木書店「南京事件資料集 中国関係資料編」南京調査研究会(編訳)
添付画像
中華門爆破の瞬間(1937年12月12日午後零時10分 PD)
中華門爆破の瞬間(1937年12月12日午後零時10分 PD)
 南京虐殺という大嘘
南京虐殺という大嘘