Image may be NSFW.
Clik here to view.
Clik here to view.

日本人は子供を神聖なものとして見ていた。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Clik here to view.

「江戸の街頭や店内で、はだかのキューピットが、これまたはだかに近い頑丈そうな父親の腕に抱かれているのを見かけるが、これはごくありふれた光景である。父親はこの小さな荷物を抱いて見るからになれた手つきでやさしく器用にあやしながら、あちこちを歩き回る。ここは捨て子の養育院は必要でないように思われるし、嬰児殺しもなさそうだ」イギリス公使 オールコック 安政6年(1859年)来日
「私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど、子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。ニコニコしているところから判断していると、子供たちは朝から晩まで幸福であるらしい」エドワード・S・モース 考古学者 明治10年(1877年)来日。
「私はこれほど自分の子供に喜びをおぼえる人々を見たことがない。(中略)他人の子供にもそれなりの愛情と注意を注ぐ」イザベラ・バード 女性旅行家、紀行作家 明治11年(1878年)来日。
英国人ジャーナリスト エドウィン・アーノルドは「街はほぼ完全に子供たちのものだ」といい、スイスの外交官アンベールは「日本人の暮らしぶりで一番利益を受けるのは子供たちである」、イギリスの書記官オリファントは「子供の虐待を見たことがない」と述べています。
民俗学者の宮本常一氏(故人)はエコノニミー(子供本位の呼称法)のあるところは非常に子供を大事にする風習がある、と述べています。一郎くんのお父さん、花子さんのお母さん、という具合に本人の名を呼ばずに子供中心の呼び方をするのがそうだといいます。
西尾幹二著「GHQ焚書図書開封」を読んでいると焚書された戦前の本の中に日本軍兵士が現地の子供に注意引く様子が出ています。以下、マレー攻略の話です。
「避難民は日本軍の幕舎の傍らを通ると、腰をおろして動こうともしない。兵隊は攻撃準備のために目がまわるくらい忙しいのであるが、可愛い子供など見ると、つい手をとってあやしたりする。開戦当初は日本兵を見ると逃げ回っていた住民たちも、今では規律正しい日本軍にすっかり慣れて、日本兵の傍らにおれば一番安心だと考えるようになっていた。そして何やかやと、兵隊の手伝いさへ自分からするようにまでなっていた」星港攻略記(昭和17年5月)
「避難民は日本軍の幕舎の傍らを通ると、腰をおろして動こうともしない。兵隊は攻撃準備のために目がまわるくらい忙しいのであるが、可愛い子供など見ると、つい手をとってあやしたりする。開戦当初は日本兵を見ると逃げ回っていた住民たちも、今では規律正しい日本軍にすっかり慣れて、日本兵の傍らにおれば一番安心だと考えるようになっていた。そして何やかやと、兵隊の手伝いさへ自分からするようにまでなっていた」星港攻略記(昭和17年5月)
上海事変の書でも日本兵が孤児となった支那の子供と遊んでいて情が移り別れが辛かったということが書かれています。日本人の子供好きは戦前まで受け継がれていました。大正9年(1920年)に日本はシベリアからポーランド孤児を救出していますが、八紘一宇の精神のほか、子供好きの日本人の心を揺り動かしたがための行動だったのかもしれません。
長岡藩城代家老の家柄だった稲田家の六女の杉本鉞子(えつこ)(明治五年生まれ)のエッセイに鉞子が初めて子供を生んだとき、母から絵本が贈られてきたときのことが書かれています。この絵本は鉞子が子供の頃に母から絵にまつわる話を聞かされたもので「剣の山」のところに印がありました。「剣の山」の話はわが子ばかりに愛情を注ぎ、他者への愛情や思いやりを忘れることを戒める話でした。母から子へ伝承していっていたのです。また、江戸時代は子育て論を書いた本は男性が男性向けに書いたものがほとんどだったといいますから驚きです。
日本人は非常に子供が好きでとても大切にしていました。他人の子供にも愛情を注いでいました。子供を中心にそえて生活していました。今はどうでしょう。個人主義で人生は自己を中心におくような時代になりました。子供の虐待がニュースを賑わす世の中になってしまいました。戦後に失われてしまった日本のよき伝統の一つでありましょう。
参考文献
小学館新書「明治人の姿」櫻井よし子(著)
徳間書店「GHQ焚書図書開封」西尾幹二(著)
岩波文庫「大君の都」オールコック(著)/ 山口光朔(訳)
平凡社ライブラリー「逝きし世の面影」渡辺京二(著)
平凡社ライブラリー「イザベラ・バードの『日本奥地紀行』を読む」宮本常一(著)
小学館新書「明治人の姿」櫻井よし子(著)
徳間書店「GHQ焚書図書開封」西尾幹二(著)
岩波文庫「大君の都」オールコック(著)/ 山口光朔(訳)
平凡社ライブラリー「逝きし世の面影」渡辺京二(著)
平凡社ライブラリー「イザベラ・バードの『日本奥地紀行』を読む」宮本常一(著)
参考サイト
WikiPedia「イザベラ・バード」「エドワード・S・モース」
WikiPedia「イザベラ・バード」「エドワード・S・モース」
添付画像
「日本兵と中国人の子供」江南地方(昭和12年11月6日) ~ 日新報道「南京の真相」より
「日本兵と中国人の子供」江南地方(昭和12年11月6日) ~ 日新報道「南京の真相」より
Image may be NSFW.
Clik here to view. 応援お願いします。
応援お願いします。
Image may be NSFW.
Clik here to view. お手数ですがこちらもよろしくお願いします。
お手数ですがこちらもよろしくお願いします。
Clik here to view.
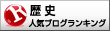 応援お願いします。
応援お願いします。Image may be NSFW.
Clik here to view.
 お手数ですがこちらもよろしくお願いします。
お手数ですがこちらもよろしくお願いします。Image may be NSFW.
Clik here to view.
Clik here to view.


